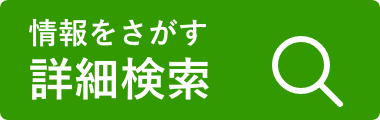農業ビジネスに潜む損害賠償リスクについて、大場弁護士が事例を交えて解説します。
なにげにサインしている契約書。そこでは、取引対象となる品種、品目、価格、納期、納入場所などの基本条件や、契約条件を満たせなかった場合の責任分担などについて規定されており、なかにはひどく一方的な記載がなされていることもあります。
ですが、親密な取引先であればいざトラブルになった場合でも話し合いで柔軟に解決できるケースもあるでしょうし、そもそも、高く買ってくれる(または安く売ってくれる)取引先との間では、あえて小難しい契約条件について交渉しようと考えない方も少なくないでしょう。
取引上の力関係から契約条件の交渉が難しい場合が多いとは思いますが、契約書にどんな内容が記載されており、どんなリスクが潜んでいるかということは、頭に入れておいて損はありません。
今回は、取引契約書を巡る基本的な留意事項について、解説していきます。
1 取引基本契約と継続的供給契約
まず、似て非なるものに、「取引基本契約」と「継続的供給契約」というものがあります。契約書の名称は様々ですが、まず、自分が締結する/している契約が、「取引基本契約」なのか「継続的供給契約」なのかの区別はしっかり認識しておく必要があります。
基本取引契約書
「取引基本契約」は、今後、両者間で行われる継続的な取引の基本事項を定めたものです。通常、この「取引基本契約」のみでは、商品を供給する(引き渡す)義務や代金を支払う義務は生じません。あくまで、「取引基本契約」を取り交わしたのちの「個別契約」(多くの場合は「発注書」のようなもの)を取り交わし、その時点ではじめて商品を供給する義務や代金を支払う義務が生じることになります。
ですので、「取引基本契約」を取り交わした場合でも、その後に発注書をもらった時点で数量や価格に不満があれば、その取引先へ商品を販売する(法的な)必要はありません。生産者とすれば、その取引先への販売価格よりも市場価格の方が高ければ、市場に販売することも(特に契約で禁止されていなければ)契約違反にはなりません。
継続的供給契約
一方、「継続的供給契約」の場合、その契約を取り交わしただけで一定の商品を供給しなければならない義務が生じます。
- この続きはアグリウェブ会員(無料)の方のみお読みいただけます。
公開日