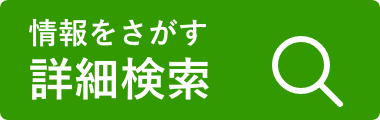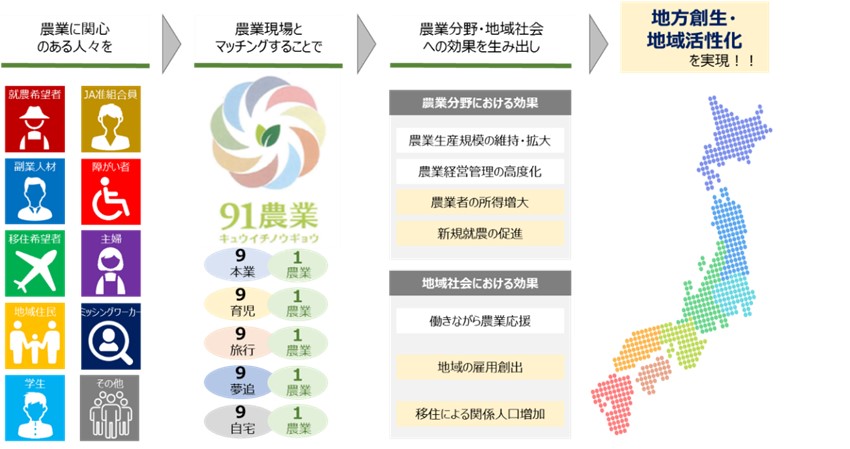更新日
労災保険特別加入制度
労災保険は、労働者の業務災害に対する補償を本来の目的としています。しかし労働者でない農業経営者であっても、作業の実態等からみて、特に労働者に準じて保護する必要があると認められる者に対して、特別加入制度が設けられています。
特別加入制度は、労働者ではないが労働者に準ずる者に対して、労災保険への加入を認め、労働災害について保護を図ることを目的として創設された制度ですから、労働基準法上の労働者は対象となりません。
農業経営者が利用できる労災保険特別加入制度
農業者が利用できる労災特別加入制度は、「指定農業機械作業従事者」「特定農作業従事者」「中小事業主等」の3種類です。原則として重複して加入することはできないので、どれか1つを選択して加入することになります。業務災害と認定される範囲は、各々で違うので、営農の実態に応じて加入することが望まれます。
指定農業機械作業従事者
自営農業者(労働者以外の家族従事者を含む。)であって、下に掲げる指定農業機械を使用し、土地の耕作又は開墾又は植物の栽培若しくは採取の作業を行う者が加入できます。
補償は、指定された農業機械を使用していた時の災害のみが対象となります。補償の対象となる農作業の範囲は、農作業のすべてではなく「農業における土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽培若しくは採取の作業」に限定され、養蚕や畜産の作業は除かれます。
|
特定農作業従事者
経営規模の大きな農業者を対象としており、具体的には、年間農業生産物総販売額300万円以上又は経営耕地面積2ヘクタール以上の規模(営農集団又は農事組合法人において上記規模以上であれば、各構成農家につき規模要件を満たしたものとして取り扱う。)で、土地の耕作若しくは開墾、植物の栽培若しくは採取、又は家畜若しくは蚕の飼育の作業を行う自営農業者(労働者以外の家族従事者含む。)であり、次表のイからホまでの作業に従事する者が加入対象となります。
イ 動力により駆動される機械を使用する作業
ロ 高さが2メートル以上の箇所における作業(40度以上の傾斜地における作業については、水平面から2メートル以上の高さがあれば、その箇所における耕作作業も対象となる。)
ハ サイロ、むろ等酸素欠乏危険場所における作業
ニ 農薬散布の作業
ホ 牛・馬・豚に接触する又はそのおそれのある作業(調教は、耕作等作業に該当しないので対象とならない。)
中小事業主等
農業の場合、常時300人以下の労働者を使用する事業主(法人の場合はその代表者)とその家族従事者等は、「中小事業主等」として特別加入制度に加入することができます。(継続して労働者を使用していない場合も、労働者を使用する日が年間に100日以上ある場合には、特別加入の対象となります。)
労働保険事務組合を通じて加入することになり、労働者に係る労働保険(労災保険、雇用保険)の事務処理を当該労働保険事務組合に委託することが条件となります。原則として、あらかじめ届け出た所定労働時間中の農作業上(畜産、養蚕、農畜産物の加工、販売を含む。)の災害が補償の対象となります。
農業の労災保険特別加入の給付基礎日額と保険料
| 給付基礎日額A | 保険料算定基礎額B(A×365) | 年間保険料 B×保険料率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 指定農業機械作業従事者3/1,000 | 特定農作業従事者9/1,000 | 中小事業主等13/1,000 | ||
| 25,000円 | 9,125,000円 | 27,375円 | 82,125円 | 118,625円 |
| 24,000円 | 8,760,000円 | 26,280円 | 78,840円 | 113,880円 |
| 22,000円 | 8,030,000円 | 24,090円 | 72,270円 | 104,390円 |
| 20,000円 | 7,300,000円 | 21,900円 | 65,700円 | 94,900円 |
| 18,000円 | 6,570,000円 | 19,710円 | 59,130円 | 85,410円 |
| 16,000円 | 5,840,000円 | 17,520円 | 52,560円 | 75,920円 |
| 14,000円 | 5,110,000円 | 15,330円 | 45,990円 | 66,430円 |
| 12,000円 | 4,380,000円 | 13,140円 | 39,420円 | 56,940円 |
| 10,000円 | 3,650,000円 | 10,950円 | 32,850円 | 47,450円 |
| 9,000円 | 3,285,000円 | 9,855円 | 29,565円 | 42,705円 |
| 8,000円 | 2,920,000円 | 8,760円 | 26,280円 | 37,960円 |
| 7,000円 | 2,555,000円 | 7,665円 | 22,995円 | 33,215円 |
| 6,000円 | 2,190,000円 | 6,570円 | 19,710円 | 28,470円 |
| 5,000円 | 1,825,000円 | 5,475円 | 16,425円 | 23,725円 |
| 4,000円 | 1,460,000円 | 4,380円 | 13,140円 | 18,980円 |
| 3,500円 | 1,277,500円 | 3,831円 | 11,493円 | 16,601円 |
(令和3年10月現在)
事業主が労災特別加入すると強制適用事業になる
労働者を使用していない個人事業主である農業者が指定農業機械作業従事者又は特定農作業従事者として労災保険に特別加入している場合は、たとえ臨時的なものであっても、労働者を雇用した場合、労働者に係る労災保険の保険関係の成立に係る手続及び保険料の申告・納付の手続を行う義務が課せられています。
また、常時5人未満の労働者を使用している個人事業主は、暫定任意適用事業であり労働者の労災保険の加入は任意加入ですが、事業主が指定農業機械作業従事者又は特定農作業従事者として労災保険に特別加入した場合は、労災保険の暫定任意適用事業ではなくなるので、労働者の労災保険への加入手続きを行うことが必要となります。
保険給付
保険給付のうち療養(補償)給付については現物支給なので、特に給付額において一般の労働者の場合と異なるところはありません。
しかし、その他の保険給付については、労働者の場合、その労働者の平均賃金に相当する額を給付基礎日額とし、これを基礎とし所定の率や日数を乗じて得られる額が給付される額となりますが、特別加入者の場合は、この基礎となる賃金がないので、これに代わるものとして、3,500円から25,000円までの範囲で定められた給付基礎日額に所定の率や日数等を乗じて得た額が保険給付として支払われることになります。
なお、この給付基礎日額は、保険料算定の基礎としても使われるので、保険料の負担や給付の額等を慎重に考慮して選ぶ必要があります。
特別支給金のうち、ボーナス等の特別給与を算定の基礎とする「ボーナス特別支給金」については支給されません。また、特定農作業従事者及び指定農業機械作業従事者については、住居と就業の場所との間の往復等の状況を考慮して、通勤災害は補償されません。
家族従事者の特別加入
労災保険制度は、原則として労働基準法上の労働者(職業の種類を問わず、事業又は事務所で他人の指揮命令下で使用され、賃金を支払われている者)を対象としているため、原則として家族従事者は補償対象となりません。
労災保険特別加入制度は、労災保険制度の対象とならない労働基準法上の労働者以外の者で労働者に準ずると考えられる者を対象とした制度です。したがって、労働基準法上の労働者ではない家族従事者も労災保険特別加入制度に加入することができます。
補償対象は加入者のみ
特別加入制度の補償対象は、特別加入した人に限られます。事業主のみ特別加入した場合には、家族従事者の労働災害については補償されません。家族従事者が補償を受けるには、家族従事者も特別加入することが必要です。
「中小事業主等」の場合は、事業主本人のほかに家族従事者など労働者以外で業務に従事している人全員を包括加入して特別加入の申請を行う必要があります。
「指定農業機械作業従事者」「特定農作業従事者」は、必ずしも家族従事者のすべてを包括して特別加入する必要はありません。希望する者のみ特別加入することができます。
労災保険特別加入の加入窓口
農業者が労災保険特別加入制度を利用する場合、「中小事業主等」では労働保険事務組合が加入窓口になり、「指定農業機械作業従事者」、「特定農作業従事者」では、個人で加入はできず、特別加入団体という団体を通じて加入することになります。
|
当該コンテンツは、「キリン社会保険労務士事務所」の分析・調査に基づき作成されております。