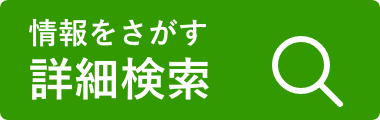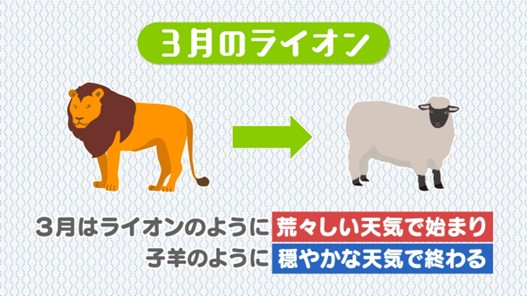(気象予報士 寺本卓也)
■今年も田植えは順調
こんにちは、農てんき予報士の寺本です。今年も早いもので、折り返しの時期ですね。
私は先月18日に福島県大玉村の「あだたらドリームアグリ」さんを訪れ、田植えをしてきました。昨年に引き続き今年の田植えも順調です。
安達太良山からの雪解け水は栄養がたっぷりで、秋には美味しいお米ができます。「心配なのは6月の低温だな。稲の生長に影響すっから。」と農家さんは心配していました。

■さつまいもの苗植えも
そして、こちらは先月26日に訪れた福島県石川町の「笑平でこぼこ農園」さん。約1.2ヘクタールの土地に30種程の野菜を栽培しています。なるべく自然なまま育てるのが特徴です。
この日は地元の小学生と一緒にさつまいもの苗植えをしました。農家の紀陸さんは、「人生は、うまくいかないから楽しい。野菜と同じくみんなでこぼこでいいんだ。」と農業を通じて思い通りにならない事の尊さを伝えていました。素晴らしい事ですよね。
さつまいもは寒さに弱く、やはり6月の梅雨時期は重要です。土の中の温度が10℃を下回ると、さつまいもはできません。東北でさつまいもを作るのは、かなりレベルが高い事なんです。

今年の梅雨はどうなるでしょうか。最近はこの梅雨がなんだか穏やかではありません。とんでもない大雨で農業分野においても大被害が発生していますよね。
今月の農てんきは大雨の原因となる「梅雨と線状降水帯」について深堀し、また最新の1か月予報もお伝えします。わかりやすく、楽しく学べる内容となっていますのでぜひ今回も最後までお付き合い下さい。

■梅雨シーズン到来 線状降水帯に警戒
最近、梅雨時期の頃に線状降水帯という言葉を耳にすることはありませんか?実はこの線状降水帯は、まさに梅雨前線ができる今の時期に発生しやすいのです。そして、この現象が発生している時は、すでに危険な状況となっていると言えます。

■梅雨前線と線状降水帯は定番セットメニュー
線状降水帯は、梅雨前線についてくる定番のセットメニューだとイメージするとわかりやすいです。梅雨前線とは、いわば春の冷たい空気と夏の暑い空気のけんかです。性質の違う空気がぶつかる事で雨雲が発生し梅雨前線ができます。北・東日本の雨の降り方はしとしと弱く降る一方で、西日本では、太平洋高気圧から暖かく湿った空気が入りやすいため発達した雨雲が発生しやすくなります。

■線状降水帯のできる仕組み
そして梅雨前線上の暖かく湿った空気が流れ込む西日本では、発達した雨雲が線状に並ぶ事がよく起きます。これが「線状降水帯」です。線状降水帯の厄介な所は、長時間にわたって同じ場所に大雨を降らせるので、災害の危険度が急激に増す事です。令和2年7月豪雨や、平成30年7月豪雨(西日本豪雨)はこの線状降水帯が大きく影響しました。

■線状降水帯は、正しい気象用語ではなかった
「線状降水帯」は、そもそも正式な気象用語ではありませんでした。実はメディアから生まれた造語です。ゲリラ豪雨や、爆弾低気圧などもその類で、いまだに正式な気象用語ではありません。ただし、それらの言葉と違うのは、気象庁はこの線状降水帯という言葉を正式な気象用語にした事です。広く世間に浸透したこの線状降水帯という言葉をキーワードとして捉え、防災に活用しようと考えたのです。

■線状降水帯の発生情報
気象庁は、昨年6月に「顕著な大雨に関する情報」の提供を開始しました。これは、一言で言うと、「〇〇県で線状降水帯が発生していますよー。」という現状を伝える情報です。線状降水帯が発生し、命に危険が及ぶような土砂災害や洪水による災害発生の危険度が急激に高まっているという事なんですね。ですから、この情報が発表された時には、以下のような行動が求められます。
・川沿いや崖など危険な場所に近づかない
・自治体からの避難の情報に基づき、周囲の状況を確かめて直ちに避難
・すでに外が危険な場合もある。垂直避難など、状況に応じて避難を行う
・気象情報・自治体からの避難情報を随時確認

■情報のレベルアップ 「線状降水帯を予想?」
そして、ここが今号のトピックです。気象庁は今年の6月1日からさらにパワーアップさせた情報の提供を開始します。
それが「線状降水帯の半日前予測」です。
これはかなり凄い情報です。その名の通り「線状降水帯による大雨の可能性を半日前に発表」するものです。最新のスーパーコンピュータを使い、世界最高レベルの技術を注ぎ込み、今まで困難とされていた線状降水帯の予想に挑戦します。
危険な状況になる事を早めに知る事で、明るい時間の避難や、大雨への備えに役立つ事が期待されます。
■大雨で畑の様子は?「キキクル」で確認を
実際に大雨が発生した場合に、今どこが危険な状況か遠隔から分かる方法があります。それは、気象庁HPで発表される「キキクル(危険度分布)」です。
これは、今いる場所が「土砂災害」や「洪水」の危険性が高まっているかどうかが、パソコンやスマホから一目で分かるようになっています。色別に危険度が分かれており、畑や田んぼ、周辺の河川の状況がわかります。
現地を見に行くのは危険がいっぱいです。まずは安全な場所から「キキクル」を活用して頂ければと思います。

■雨の降り方と災害の目安
また今回はあまり他で聞く事ができない気象予報士ならではのスキル、雨の降り方と災害の目安という物をお伝えします。よくテレビで、予想される雨量は〇ミリというのがありますが、数字だけ聞いてもピンとこないですよね。そんな時の雨量のイメージとなります。
① 1時間に100ミリの雨は「都市部などの河川で増水、低地の浸水」が発生。
② 2〜3時間で200ミリの雨なら、「急傾斜地の土砂災害」が発生。
③ 12時間で400ミリの雨なら「大きい河川の氾濫、土砂災害多発、農業用ため池損傷・決壊」が発生。
あくまで目安ですが、是非今後の参考になればと思います。

■今年の6月は大雨注意か?
最新の1か月予報で降水量を見てみましょう。すると西・東日本を中心に降水量が平年並みか多い予想となっています。やはり今年も大雨に注意が必要となりそうです。

■蒸し暑い6月 病虫害多発に注意
さらに、気温も見てみましょう。すると今度はほぼ全国的に平年並みか高い予想です。雨や曇りの日が多く日照時間が少なくても、西・東日本はジメジメそして、蒸し暑く感じられるかもしれません。今月は病虫害の多発にも注意したいですね。

シリーズ『農てんき予報〜農業に役立つ天気の情報〜』のその他のコラムはこちら
当該コンテンツは、担当コンサルタントの分析・調査に基づき作成されております。
公開日