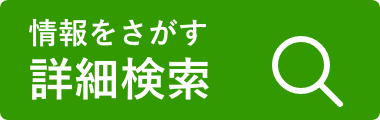(一社) 農業利益創造研究所 理事長 平石 武
はじめに
「農業利益創造研究所」は、農業簿記ソフトのトップメーカーである「ソリマチ株式会社」から、統計利用を承諾してもらった会計ビッグデータを提供してもらい、「データ分析による所得向上の気づき」を情報発信しています。
このコラムでは、2021年の13,300件の個人事業農家データを集計した分析を行っていますので、農業者の方はご自分の経営と比較しながらご覧ください。
持続可能な農業経営とは
前回のこの連載コラムは、「持続可能な農業経営」とは<耕種農業編>」を掲載しましたが、今回は「畜産農業編」です。
前回も触れましたが、近年「持続可能な社会・農業」という考えが注目され、農林水産省でも「みどりの食料戦略システム」を策定し、環境に配慮した農業や、有機農業の推奨を行っています。
しかし、持続可能な農業は環境配慮だけでなく、経営が発展・継続し、農家数が維持していかなければならず、そのためには経営の収益性や安全性、そして後継者の存在が重要であると考えます。
これらについて、農業簿記ユーザーの中で、酪農、肉用牛の個人事業畜産農家820件のデータを分析して、持続可能な農業経営の姿を探ってみたいと思います。
畜産経営は売上3億円に節目がある
持続可能な農業経営は、何と言っても経営継続できる所得額と、高い農業所得率(効率性)が重要です。収入金額規模別に、雑収入と世帯農業所得額(控除前農業所得+専従者給与)と世帯農業所得率(収入金額に対する所得額の率)をグラフにしてみました。
まず、酪農経営では、収入金額の上昇とともに世帯農業所得額が高くなっていきますが、3億円のところで雑収入額が所得額を超えています。雑収入は奨励金や交付金を含んでいますので雑収入が無ければ経営が成り立たないことがわかります。また、農業所得率は2,000万円から平行線となっていますが、1億円を超えるとダウンしています。
そして、3億円以上になるとなぜか所得額も所得率も急にアップしています。これはあきらかに収入3億円に節目があり、個人事業としての経営と、設備投資や雇用を入れる企業的経営の分岐点であろうと考えられます。この3億円の節目を意識した経営が持続可能性につながっていくのではないかと思われます。

肉用牛も雑収入が多いです。所得率でみると小中規模経営の方が効率的であり、3億円以上になると所得率が6.6%とかなり低くなっていますので、所得率が低いということは経費が高いということですので、現在の所得額が高くても、もし売上が減少した際のリスクは大きくなると想像できます。
やはり、肉用牛も収入3億円を節目として経営戦略を考えた方がよさそうです。

高所得経営の特徴は
それでは、高所得経営と低所得経営では何が違うのでしょうか。
世帯農業所得3,000万円の高所得農家と、400万円の低所得農家の、収入金額を100とした収入と経費の比率を出して、その差(高所得ー低所得)をグラフにしました。
酪農の高所得経営は雑収入が低く、素畜費が高く、減価償却費が低い、というような特徴はありますが、なんといっても飼料費が低いことが大きな差になっています。おそらく高所得農家は飼料を購入せずに自給飼料なのではないかと想像できます。
現在国際情勢の影響により飼料価格が高騰していますので、このままだと低所得酪農農家の経営はさらに厳しくなる可能性があります。

肉用牛の高所得農家の特徴は、素畜費と飼料費が高いことです。推測ですが品質が良く高く売れる牛肉を生産するために、血統が良く価格が高い子牛を購入し、良い飼料を食べさせているのかもしれません。それだけ経費をかけても高く売れて所得が大きいということなのでしょう。

高所得経営と安全性の関係はどうか
持続的経営には資金繰りがうまく回って倒産しないことも大事です。貸借対照表の中の現預金、固定資産、借入金に着目し経営の安全性についてみてみましょう。
以下のグラフのように、世帯農業所得が増加しても折れ線グラフはギザギザしていて大きな変化は無いように見えます。しかし、所得3,000万円の階層では借入金率(借入金は1,600万円)が低く、現預金率が高くなっているのに、3,000万円を超えると固定資産額と借入金(1億1千万円)がぐっと増えています。おそらくこの階層は、設備投資をして企業経営的な経営なのだと思います。所得が高いことは良いことですが、経営の安全性的にはリスクがあるとも言えます。

肉用牛農家は、所得が高くなるにつれ安全性が高くなっています。ただ、所得3,000万円の経営は借入金が7,300万円と高くなっていて、3,000万円を超えると安全経営になっています。理由は不明ですが、酪農経営と肉用牛経営は、所得3,000万円に節目があると思われます。

年代別の収益性の特徴は
持続可能な個人農業経営を考えるうえで最も重要なことは、後継者が経営を継承し、若い世代の就農者が増えていくことですから、次に年代別の特徴を分析してみましょう。
酪農農家は若い世代の収入金額が高く、固定資産投資をして、借入金も高くなっています。若い世代の挑戦意識が高いことは将来に期待が持てますが、飼料等が高騰していますのでより一層安全性を意識した経営が望まれます。
肉用牛農家の収入や所得は、年齢が上の世代の方が良いようです。おそらく肥育技術が高いからだと思われますが、でも、酪農と同様に若い世代の固定資産投資が高く挑戦意識がありますので、未来は明るいかもしれません。


持続するには後継者が絶対必要
持続するために絶対必要な後継者について分析してみました。農業簿記ユーザーの青色申告決算書の中の「専従者給与の内訳」の続柄が、子、長男、長女などと書かれている人はおそらく後継ぎであろうという判断で、抽出分析してみたところ、65歳以上の経営体で後継者がいる割合は、酪農が48%、肉用牛が29%でした。酪農の後継者がたくさんいるのは喜ばしいことです。
後継者がいる農家の収入金額と世帯農業所得の平均を集計してみると、下記の表のようにとても高い金額となりました。やはり世帯農業所得が1,000万円を超えるくらいの経営であれば他産業と見劣りしない金額ですので、子供も後を継ごうと思うのではないかと思われます。

まとめ
経営を継続していくには収益性と安全性が高く、設備投資と借入金のバランスがとれていることが重要です。酪農も肉用牛も売上3億円あたりに分岐点がありますので、経営継続していくには個人事業経営で効率的に経営するか、企業的に経営するかをよく考えて、そして所得アップを目指しながら後継者を育てていくことが大事かと思います。
牛乳の消費が減り、コロナ禍の影響でインバウンド(訪日外国人)の減少による和牛消費が減り、さらに飼料価格の高騰というダブルパンチの状況です。
しかし、外部環境をしっかり把握しその環境変化に合わせて柔軟に経営していくことで必ず持続可能な農業経営を実現できると思います。
連載は今回で最後です。お読み頂き、ありがとうございました。
当該コンテンツは、一般社団法人 農業利益創造研究所の分析に基づき作成されています。
シリーズ『農業会計ビッグデータから見える!高所得農業経営とは<2021年データ版>』のその他のコラムはこちら
当該コンテンツは、担当コンサルタントの分析・調査に基づき作成されています。
公開日