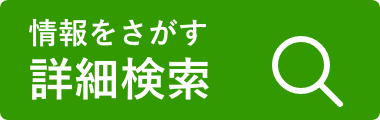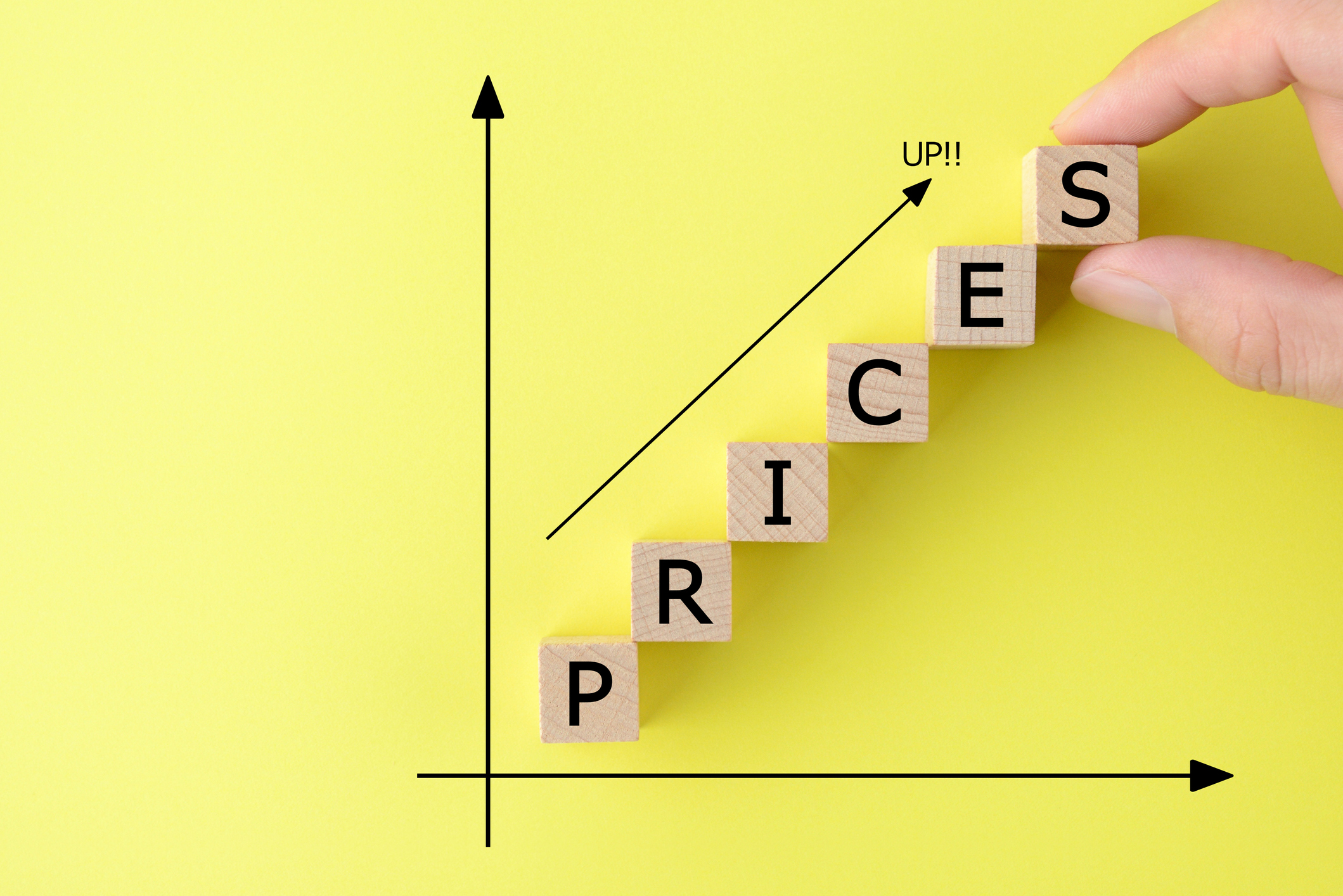(日鉄ソリューションズ株式会社 清水翔太郎)
改めまして、日鉄ソリューションズ株式会社の清水翔太郎です。前回の記事では、サツマイモ選別システムの開発に至った背景や、農福連携におけるITの役割について紹介いたしました。
今回は、私たちが現地の農家様と連携しながら実証を進める中で感じた「企業と農家が直接つながり実証する意義」について三点に分けてお伝えします。
1.農業現場で作業を実体験できたこと
一点目は、農業現場で作業を実体験できたことです。私たちの農作物選別システムの開発プロジェクトは、農家様やAct.のスタッフと直接対話したり、農家様で様々な農作業を実際に体験したりする中で得られた気づきから始まっています。
特に、初めて徳島を訪問した際には、サツマイモの選別作業のみならず、草取り作業やサツマイモの収穫作業やイチゴの葉取り作業(古くなった葉や傷んだ葉を見つけて取り除く作業)などを体験させていただきました。
こうした経験の中で、私たちは最初にITでサポートすべき作業としてサツマイモの選別作業を選びました。その理由として、草取り作業や収穫作業は知的障がいのあるAct.のメンバーでも十分に貢献できており、イチゴの葉とり作業は経験や勘を必要とされる難易度の高い作業であるうえ、ビニールハウス内を動き回るためシステムを一か所に設置するのが難しいと判断したことが挙げられます。
これらの作業についても、当初はパワードスーツ(人間が着用して力仕事をサポートする装置)で力仕事を補助する案や、AIやARグラス(メガネ型のディスプレイに情報を表示するデバイス)を活用してイチゴの古くなった葉や傷んだ葉を視覚的に作業者に提示する案などがありましたが、最終的にはAct.のメンバーが抱える課題(経験や勘を必要とする作業があまり請け負えていないこと)や、システム導入の難易度、徳島における仕事の量などを総合的に勘案して決定しました。
ただし、現時点で対象にしていない作業であっても、今後の展開によっては取り組む可能性はあると考えています。
イチゴの葉取り作業

2.農家の協力によりデータを効率よく収集できたこと
二点目は、農家様のご協力によってサツマイモの画像データを効率良く収集できたことです。
前回の記事でも述べた通り、AIの学習には大量のサツマイモのデータが必要になります。特に、異常のあるサツマイモはスーパーマーケットなどの一般的な流通では入手困難でしたが、農家様を直接訪問してサツマイモを撮影したり購入したりすることで多種多様な異常データを収集できました。
農家様との直接的なつながりがなければ、学習データの充実は困難を極めていたと感じます。こうした機会を持てたおかげで、例えば黒斑病という外皮に黒い窪みのようなものができる病気のサツマイモや、一部だけ極端に凹んでいるサツマイモやS字にカーブしたサツマイモといった、現場以外では、ほとんど見られない異常データを収集できたことは、AIモデルの精度向上に大きく貢献しました。
黒斑病のサツマイモ

一部だけ極端に凹んでいるサツマイモ

3.現場の農家によるフィードバックを得られたこと
最後の一つは、現場の農家様によるフィードバックを得られたことです。
仮にシステムとして不具合がなかったとしても、現場で活用されなければ意味がありません。私たちは、選別システムを使用している様子や選別の結果を実際に農家様にお見せして、判別のスピードや正確さなどについてフィードバックを収集しました。さらに、時には「全体を一度に判別したい」「2秒以内で判別を終えたい」といった農家様ごとの個別のニーズに応えるため、複数のバージョンを開発するといった対応も実施しました。
こういった現場のニーズによって生まれた機能は、現場での活用に即したものになっていると確信できますし、実際に良好なフィードバックをいただいています。また、現場で得られるフィードバックの価値は、単なる技術改善に留まりません。
農家様からの「この部分が役立った」という具体的な声は、私たちにとって大きな励みであり、プロジェクトを進める原動力となっています。

プロジェクト発足当初からお世話になっている徳島県内の農家様やAct.の方々(一番左、一番右は弊社メンバー)
農業の未来に希望をもたらす一助となることを願って
日本の農業は高齢化や後継者不足といった課題を抱えていますが、企業と農家が直接協力しながら新しい技術で現場の課題を解決する取り組みは、農業の持続可能性を高めるための重要な鍵になると考えています。
一方で、技術だけでは解決できない課題もあります。私が本記事で取り上げた三つの「企業と農家が直接つながり実証する意義」は、いずれも現在の技術をもってしても代替が難しく、かけがえのないものです。
この取り組みが、農業の未来に希望をもたらす一助となることを願いながら、今後も活動を継続していきたいです。
シリーズ『企業と農家がつながり実証する意義』のその他のコラムはこちら
当該コンテンツは、担当コンサルタントの分析・調査に基づき作成されています。
会員登録をすると全ての「コラム・事例種」「基礎知識」「農業一問一答」が無料で読めます。無料会員登録はコチラ!
公開日