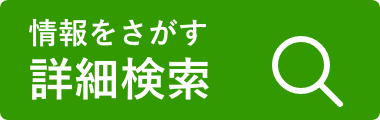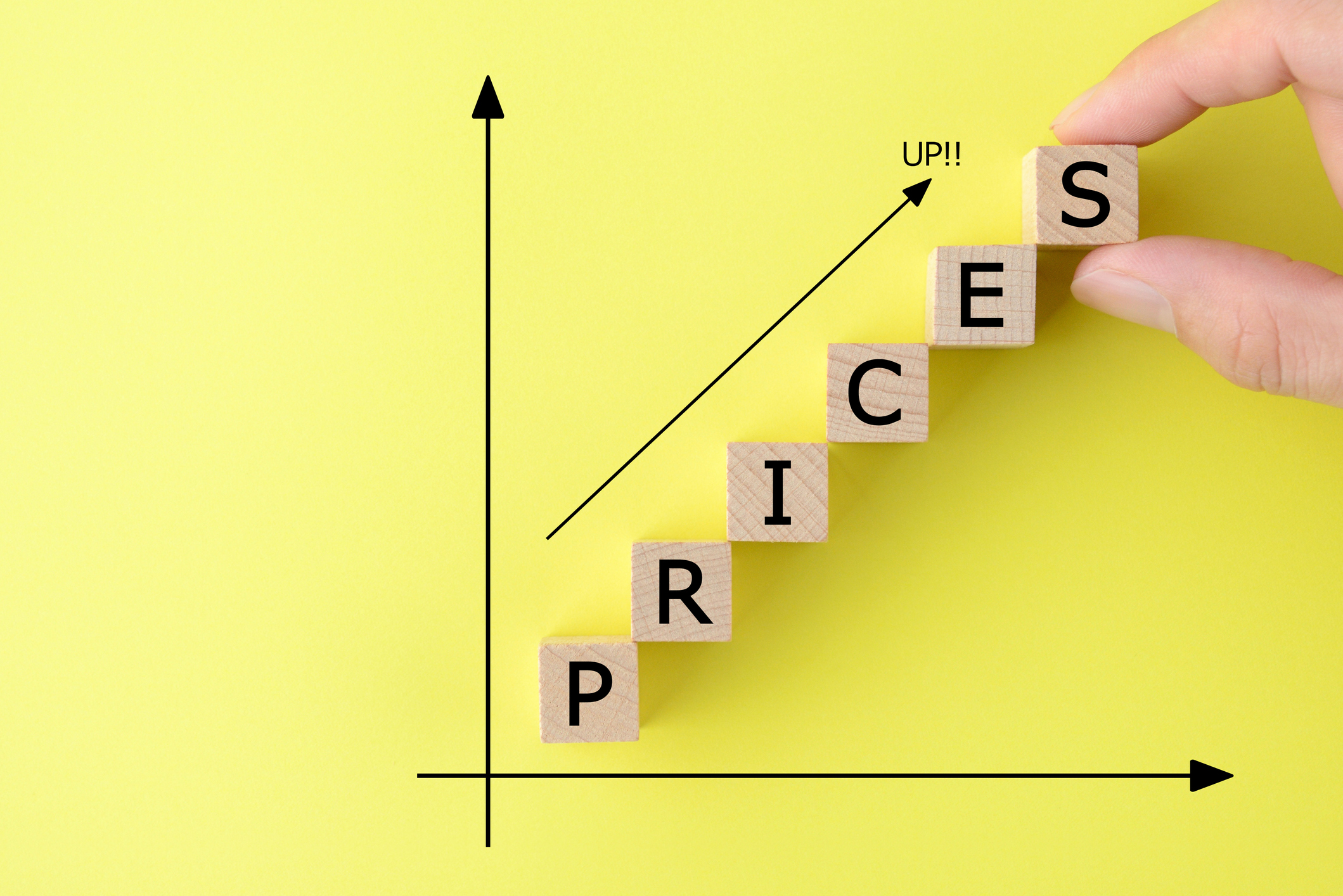更新日
1.間接輸出と直接輸出
一般的に流通は、「商流」、「物流」、「情報流」という3つの流れによってできています。
「商流」は取引(商談)の流れであり、カネの流れです。「物流」は商品をどのように届けるかというモノの流れです。「情報流」は商品や生産者に関する情報の流れです。この3つの流れが揃うことで流通が形成されています。
食品の輸出を考えるうえでは、特に商流と物流について検討を行う必要があります。商流の作り方によって、輸出は大きく2つに分けられるためです。
ひとつは商流として輸出商社を活用する「間接輸出」であり、もうひとつは生産者・メーカーが直接輸出を行う「直接輸出」です(下図)。

ここでの重要なポイントは、食品輸出の商流において、輸出商社と輸入商社(インポーター)という2種類の商社が存在することです。
輸出商社は、国内で生産者やメーカーから商品を調達することがメインの商社です。複数のメーカーの複数の商品を取り扱い、まとめてインポーターとの商談や物流の手配などを行う企業です。輸出先の現地に支店を持っている国内企業も少なくありません。
インポーター(輸入商社)は、現地で輸入商品の調達を行う商社です。輸出商社から仕入れを行う場合もあれば、産地やメーカーを訪問して直接取引を行う場合もあります。日本に支店を持つ海外企業もあります。
ここで知っておきたいのは、当然ながら商流に輸出商社やインポーターが介在する場合は、その企業の数に応じて最終的な消費者への提示価格が上昇していくことです。
なお、一部の商品カテゴリーでは、流通構造調査がジェトロによってなされており、商社に委託するプロセスごとに細かくコストを試算できるようになっています。
ラベル添付や成分検査等を商社に代行してもらうほどコスト増につながるため、自社(自分)で実施できる/するべき内容と、外注するべき内容について検討しておく必要があります。
この自社で実施できる内容、するべき内容を精査し、輸出に向けた商流と物流の検討を進めていく上では、「間接輸出」と「直接輸出」のメリット・デメリットについても知っておく必要があります。それぞれのメリット・デメリットは以下のとおりです(下表)。

なお、輸出への取り組みが初めての場合は、自社内に輸出のノウハウが無いため、間接輸出の方が実施しやすいと言われます。
一方、自社スタッフの育成とノウハウ整備が進んだ場合や、輸出量が多くなった場合などは、コストなども含めて直接輸出の方がメリットが大きくなると考えられます。
2.商社との付き合い方
輸出商社との付き合い方
まず、日本国内企業が中心となる輸出商社との付き合い方としては、WIN-WINとなれる関係を構築することが前提となります。具体的な付き合い方法を以下に3つ示します。
① 商品に対する思い、戦略をきちんと伝える
マーケティング用語は世界共通であるため、ターゲット顧客や差別化のポイントなどを明確にして、しっかりと輸出商社にも説明しましょう。
② 一緒に汗をかき、きちんと情報収集を行う
必要に応じて商社の営業にも同行しましょう。バイヤーのニーズを把握し、改善策を商社と共に検討することで、パートナーになることができます。
③ 相手の立場に立つ
輸出商社を活用する場合、その企業が「売りたくなる・買いたくなる」商品であることも非常に重要な要素です。「輸出商社の立場」で利益創出まで考えた提案ができるとベストです。輸出のマーケティングの検討において、最終消費者や現地バイヤーだけでなく、商社もステークホルダー(利害関係者)として考慮に入れておくことが望ましいでしょう。
インポーターとの取引のポイント
次に、現地で輸入を手掛けるインポーターとの取引の3つのポイントを以下に示します。
① 役割・範囲の明確化
商品の受け渡し条件、自社で用意すべきことの明確化とコスト(納入価格)への反映をしっかりと行いましょう。ここでの交渉が出来ていないと、販促用の資材の供給を延々と要求されたり、店頭イベントに毎回立たされたりするようなことも少なくありません。
② 商品の背景などを丁寧に伝える
商品の背景・ストーリー、意味的価値、利用シーン、利用方法を商談時から丁寧に伝えていく必要があります。利用シーン、利用方法の相互理解が不足していると、インポーターから小売バイヤー等への商談がうまくいかなかったり、置かれるべき売場などが適切でなくなる可能性もあります。
③ サポートベンダーの活用
英語等での取引に不安がある場合は、営業・商談代行企業・貿易実務代行企業などもあるので、適宜活用を検討しましょう。ただし、サポートベンダーの活用はコストがかかり、輸出商社を活用する方が結果的に良い場合もあるため、注意が必要である。
インポーターや輸出商社の探し方
最後に、輸出を実現するためのインポーターや輸出商社の探し方について触れておきます。積極的に自分から商社が居る場所に出向いていくことが基本となります。
① 商談会等での輸出に向けた商社の発掘
商社の発掘は、商談会や展示会で行うことができます。直接、出展しているときに名刺交換をした方はもちろん、商談会や展示会で知り合った現地小売バイヤーから商社を紹介してもらうことなども可能です。あるいは、同じ商談会に出展する日本の企業などに声をかけ、その方が使っている商社などを紹介してもらうことも視野にいれましょう。
② JETRO・進出予定国の政府機関の活用
JETROなどの進出予定先の日本の出先機関などに問い合わせを行い、進出予定国の投資・産業関連省庁の日本事務所などを活用して探します。
以上、海外輸出の実現においては、商流と物流の構築が非常に重要な要素です。こと商流においては、間接輸出にするか、直接輸出を目指すかといった検討から、商社を探して、どのようにお付き合いしていくかまで検討するべき内容は国内よりも多くなります。
具体的な検討を進めていくにあたり、少しでも情報はリアルで、先端のモノである方がよいため、展示会や商談会への積極的な参加が第一歩と言えるでしょう。
当該コンテンツは、公益財団法人 流通経済研究所 農業・地域振興研究開発室 折笠室長の分析に基づき作成されています。